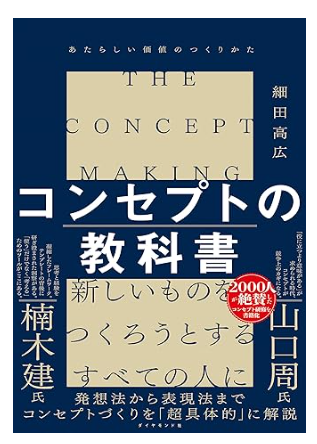企画書の書き方|外資コンサルの考え方実例有
- Z
- 2026年1月1日
- 読了時間: 34分

※当記事にはPRが含まれています
当記事では、外資系コンサル出身者が監修した「企画書の書き方」を中心に解説したいと思います!
持続的に企業・事業を成長させていくためには、事業機会創出/オペレーション効率化等のための企画書や、新規案件獲得のための提案書の作成は避けられないかと思います。
ですが、企画書・提案書の作成に関して、プロフェッショナルから適切な指導を受けたことがある人材は多いとは言えず、現場で試行錯誤しながら作成し、技術習得をしているのが実情ではないでしょうか。その結果、作成したはいいものの、検討内容自体に抜け漏れがあったり、納得感のないストーリー構成となってしまっていることで、下記のような問題が起こっている事例をよく目にしてきました。
例えば、
関係者の合意・意思決定を円滑に取り付けられず、無駄な資料作成や手戻りが頻発した
経営陣に企画の内容をうまく伝えられず、企画自体がボツになってしまった
顧客に提供商品/サービスの価値をうまく伝えられず、何度も失注した 等
そこで当記事では、企画書や提案書を無数に書いてきた「元外資系コンサルタント」の知見をふんだんに盛り込み、「企画書の書き方」を解説したいと思います。
必要なスキルを身につけたあと、“どこで年収を最大化するか?”でキャリアは大きく変わります。 あなたはどの方向に進みたいですか?
コンサル転職
⇒圧倒的な問題解決力とプロジェクト推進力が得られる。「個」としての基礎戦闘力を極限まで高める修行の場
フリーコンサル独立
⇒自分の専門性を軸に、「月単価150〜250万円」の報酬と、時間の自由を得られる。会社に中抜きされず、スキルの対価をダイレクトに受け取る稼ぎ方
大企業/スタートアップ、PEやVC
⇒「事業を動かす」当事者としての経験と、ストックオプション等による資産形成(アップサイド)が得られる。アドバイザーからプレイヤーへの転身
企画書の書き方の監修者
監修者名 | 監修者プロフィール |
外資 コンサル Z | ・外資系コンサルティングファームにて、戦略策定、新規事業、M&A等のPJに参画 ・複数のスタートアップの経営陣を経て、フリーコンサルとして独立 ・大企業やスタートアップの経営企画部の立ち上げや、企画書・事業計画書・提案書作成を多数支援 |
当記事「企画書の書き方」の目次
1. 企画書の書き方を学ぶ前に:そもそも企画書とは?
そもそも企画書とは何なのでしょうか。私は、企画書を「現状の課題や市場環境の変化を踏まえ、今後必要となる新規の取り組み案を落とし込んだ『社内意思決定用の施策資料』」だと考えています。
例えば、下記のようなものが企画に該当するかと思いますが、「企画」は属している業界・業種等によって、無数に存在します。
ブロックチェーンを活用した新規事業企画
人件費削減へ向けた報酬制度の見直し企画
海外展開を見据えた組織構造の変革企画
AAA社 事業計画
2. 企画書の書き方を学ぶ前に:事業計画書、提案書、報告書との違い

上記画像にあるように、ビジネスで用いられる資料は、大きく下記3つで分けられます。
企画書
提案書
報告書
企画書とは
前段で見たように、「現状の課題や市場環境の変化を踏まえ、今後必要となる新規の取り組み案を落とし込んだ社内意思決定用の施策資料」のことでした。事業計画書はざっくりと言えば、上記企画書に含まれると考えてよいでしょう。
事業計画書とは
事業計画書とは、企画書の内容を具体的な計画レベルまで落とし込んだものであり、それが事業として収益を生み出す単位として考えられる際に作成されます。
例えば、下記のようなものです。
会社単位:AAA社 事業計画書
事業部単位:BBB事業 事業計画書
具体的な事業計画書の書き方は下記記事をご参照ください。
提案書とは
提案書とは、「他社(含. 顧客)に対する自社/自社サービス・製品の訴求資料」と定義できます。(※ラフな企画書と定義されることもあるが、社外向け資料と定義されます)
つまりそれは、顧客(主にB2B)に対して、製品/サービスを導入・購買してもらう際に、訴求ポイントや価格等をまとめた資料です。
また、事業拡大等を目的として、他社に対して協業・提携等を提案し、提携時のシナジーや提携スキーム等をまとめた資料等のことも指します。
例えば、下記のようなものです。
クラウド会計サービス「CCC」 導入のご提案
Webマーケ支援のご提案
コスト削減支援のご提案
富裕層領域取り込みへ向けた協業のご提案
報告書とは
報告書とは、「企画書・提案書内の取り組みの成果・進捗に関する説明資料」のことです。提案書でプロジェクト等を受注した場合には、報告書を「提案先」に提出することとなります。社内での企画書であれば、中間や最終の報告書を「社内経営陣」 等に共有することとなります。
提案書や企画書で組成されたプロジェクトについては、プロジェクトのキックオフ以降は、通常マイルストーンごとに成果・進捗が報告され、次回のマイルストーンまでのアクションも示されます。
例えば、下記のようなものです。
報酬制度見直しの中間報告書
XX領域強化へ向けた買収候補ソーシング状況の報告
3. 企画書の書き方を学ぶ前に:企画書を書く際の問題・課題

企画書作成時・承認時には以下3つのステップで様々な問題が起こります。
まず、「内容健康・具現化」のステップです。ここで起こる問題は下記のような問題です。
情報収集に終始し、情報に溺れ、企画としてまとまらない
アイデアを具体的にうまく描き出せず、ひたすら悩んでいる
次に、「資料への落とし込み」のステップです。ここで起こる問題は下記のような問題です。
体裁・見せ方にこだわりすぎ、何度も色や形を修正し続ける
PPT操作に不慣れなため、資料作成自体に時間を要している
最後に、「報告・意思決定」のステップです。ここで起こる問題は下記のような問題です。
指摘・修正箇所が多すぎて、修正作業にうんざりする
上長から納得感が得られず、手戻りが発生してしまっている
このように、何度も同じ問題が起こる理由は、「型」 (思考・資料作成)を習得できていない、かつ実践知化できていないためです。つまり、企画立案時に、このような問題が起こらないようにするためには、下記2つを行なう必要があります。
「型」 (思考・資料作成)の習得
実践知*化(*:現場・実務の状況に即して判断・柔軟に対応できること)
4. 企画書の書き方
a. 企画書の目次は何がいいの?
企画書の最低限の構成要素としては下記です。このほかにも必要な項目もありますが、それは場合により判断し、追加していく流れかと思います。
①背景・目的
②企画案 (全体像・詳細)
③企画を実施すべき理由
④企画を実施した際のインパクト
⑤必要リソース(ヒト・モノ・カネ)
⑥プロジェクト体制
⑦プロジェクトスケジュール
経営陣や部長レベルが納得し、気持ちよく意思決定できるように、企画を行なう際には少なくとも上記の内容を網羅しておく必要があります。提示された「企画案」の中身に関して、判断に必要な情報で抜け漏れがあった際には、再リサーチの必要性や作業の手戻り、最悪の場合にはせっかくつくった企画がボツに追いやられるケースもあります。
b. 企画書の各ページの具体的な内容は?
それでは、一つ一つ上記目次に沿って説明していきたいと思います。
①背景・目的
まずは、当企画を行なうにあたっての背景と当企画・企画書の目的を箇条書きでもよいので、シンプルに示しましょう。この段階で意思決定者との共通認識を作っておくことは必須です。前提がずれていると、確実に後々しょうもない理由でひっくり返されることがあります。
【スライドの方向性 ※背景・目的スライドの例】
弊社コンテンツの例で大変恐縮ですが、下記画像のように「背景」と「目的」という形で構造的に分け、ビュレットポイントで簡潔に示すというやり方を外資系コンサルタントはよく行ないます。

②企画案 (全体像・詳細)
わかりやすく「企画案」と表現していますが、実際は「XXX企画」「企画案:XXX」等の名称に変更してもらえればと思います。企画書を書いていく際に、何より重要なのが「②企画案 (全体像・詳細)」となります。具体的に、どの領域/機能で、何を行なっていくのかを具体的かつシンプルに示しましょう。企画は大まかに、下記2つに分けられると思います。
「マイナスな状態」を「正常・プラスな状態」にもっていく
「正常・プラスな状態」を「さらなるプラス」にもっていく
一つ目の「マイナス状態の改善」の企画・提案に関しては、現状を正しく理解することが先決です。正しい現状認識の下、原因深掘・課題設定を行ない、問題の根源を解消する打ち手を立案しましょう。
二つ目の「プラス状態のさらなる発展」の企画に関しては、未来に対する独自の洞察が企画・提案のユニークネスを左右します。来るべき未来を見据え、自社/顧客がいかなる変化をすべきかを提示しましょう。
例えば、「人件費削減へ向けた報酬制度の見直し企画」を行なう際には、「人件費の状態が他社平均等と比べ、悪い(≒ベンチマークと比べ、構成比が高すぎる)」というマイナスな状態があって、「報酬制度を見直す」という企画によって、改善を図るといったことが考えられます。
また、その企画が「最も人件費の改善に寄与する」という前提のもと、経営陣等に提示することになるかと思います。当パートでは、「報酬制度」をどのように見直すのかを具体的に示しましょう。報酬制度の見直しなので、例えば下記のような施策を説明する感じでしょうか。
昇給額を10%引き下げる
各グレードの給与レンジを主要競合であるXXXと同等まで落とす
変動インセンティブの掛け目をXX%下げる
加えて、上記施策を実現する上で、具体的に何を行なっていくべきなのかも併せて記載・表現するようにしましょう。
【スライドの方向性】
スライドの表現方法としては様々ありますが、意思決定者にとって魅力的にうつるように、一目で概念や世界観のわかるポンチ絵のようなスライドを準備するとよいでしょう。細かな文字の羅列や数字の羅列だと企画の世界観が伝わりづらいため、まずはポンチ絵等でぱっと伝え、細かな個別施策や定量データ等は後続スライドにまわしましょう。
③企画を実施すべき理由
「②企画案 (全体像・詳細)」について、ただ「これがやりたいです!」と叫ぶだけでは、だれも意思決定などできません。「収集したファクト」を構造的に整理しながら、より説得力あるストーリーで「なぜその企画を貴重なリソースをかけてやるべきなのか」を伝える必要があります。
例えば、「自社の営業生産性を向上させるために、何らからのSaaSプロダクトの導入を考える」という企画書には、少なくとも下記には答える必要があるでしょう。
導入によって、自社にどのようなインパクトがあるのか
導入にあたってのハードルは高くないか
また、「新たな市場への参入」の企画に関しては、以下のような論点に対する答えは収集しておく必要があります。
その市場が他の市場と比べどのくらい魅力的なのか
自社として参入して勝てるのか
参入にあたっての難易度は高くないか
上記論点のカバー範囲とその深さが甘いと、経営者や部長レベルは判断・Go/No Goの意思決定ができません。つまり、いかにおもしろい企画であっても、それが「なぜやるべきなのか」という情報もセットでなければ、それはボツ企画になってしまうということです。「企画」を行なう際には、何をサポート材料として提示できれば、納得し、気持ちよく意思決定してもらえるかを一度考えてみましょう。
【スライドの方向性】
ここでは定量データや定性データを用いた様々な表現方法が想定されます。競合との比較でしたらコア数値はグラフで比較したり、機能充足状況だったら比較表をつくることも有効でしょう。
④企画を実施した際のインパクト
ここでは企画案を実施した際のインパクトを定量的に表現します。例えば、人件費水準適正化のための報酬制度の見直しの事例だったら、下記のような施策を実施した際に、
昇給額を10%引き下げる
各グレードの給与レンジを主要競合であるXXXと同等まで落とす
変動インセンティブの掛け目をXX%下げる
「どのくらい総額人件費が引き下がるのか」ということがインパクトとして表現されるはずです。また、「他の市場への参入の企画」だったら、参入した際に創出できる「売上高」や「新規顧客数」となるでしょう。加えて、必要コストまで計算できているのであれば、「貢献利益」といったことも示すことができるはずです。
【スライドの方向性】
ここでは、できる限り定量的なグラフ(棒グラフや折れ線グラフ等)でもって伝えることが肝要です。
⑤必要リソース(ヒト・モノ・カネ)・⑥プロジェクト体制
企画案、サポート情報、インパクトを表現できたら、その理想的な企画案を実現するために「どれだけのヒト・モノ・カネが必要なのか」も定量的に表現しましょう。企画案が大規模なものだった場合、一人の力じゃ実現できないはずです。実現へ向けて、どこの部署の×どのような人材が×どれだけ必要なのか、をその理由と共に表現しましょう。
ここでしっかりとリソースを要求できていなければ、素晴らしい企画案を作成できていたとしても、その実現が大変困難となってしまいます。
大企業でよくある例ですが、新規事業案を全社として考えさせたときに、いくつか良い案は出て、一部の案は検討が開始されることがよくあります。しかし、結局実現せず、いつの間にか消えていくといったことがtあります。
結局、できない理由/やめたほうがいい理由をあげることのほうが簡単なので、企画の実行状況が芳しくなければ、「費用対効果が!」「別にもっと取り組むべきことがある!」だの社内の評論家から刺されてしまう結果につながります。そのため、企画案の具体化や企画案の実行自体を確実なものとするため、必要となるリソースは過不足なく集めておく必要があるのです。
【スライドの方向性】
ここでは、必要リソース量は表形式に縦軸に項目を並べ、概要と必要経費の概算を簡単に示しましょう。体制図についてはよくあるツリー構造で示し、オーナーやメンバーがどこのだれかを示しましょう。
⑦プロジェクトスケジュール
最後に、実現までのスケジュールです。ここでは企画案を実行した際に、「いつまでに」×「なにをやっていくのか」を表しましょう。そして、一定の期間ごとでマイルストン(中間報告、最終報告)を設定し、そこでどのようなアウトプットを出す想定なのかも併せて表現しましょう。
【スライドの方向性】
ここでは箇条書きではなく、ガントチャートの形式で縦軸に大まかなタスク、横軸には月や週等の時間軸を設定しましょう。その中でいつ、だれに対する報告会があるのかのマイルストンを示しておくとよいでしょう。
c. 企画書の書き方のポイントは?

企画書作成のポイントは、「顧客/自社の現状・今後の見立てを踏まえた「解」を、納得感のあるストーリー・スライドでクリアにメッセージングできるかどうか」となります。そしてそれは、「円滑に合意・意思決定を獲得するための条件」となります。具体的には、「What:何を伝えるか」×「How:どのように伝えるか」の二つを漏れなくおさえておく必要があります。まず、「What:何を伝えるか」ですが、「顧客/自社等の現状や今後の見立てを踏まえ、必要な打ち手(企画・提案)を導出できているか」がポイントとなります。
顧客/自社の現状、今後の市場の見立てを正しく捉えられているか
上記を踏まえ、今後の成長・目標実現へ向けた課題を抽出できているか
課題に対する解(企画案/提案)が論理的かつ独自の視点・洞察を踏まえ、導出されているか
次に、「How:どのように伝えるか」ですが、「ストーリー・スライドによって、理解・納得感を醸成し、円滑な意思決定を促すことができているか」がポイントとなります。
「解」がメッセージとしてシンプルに提示されているか
納得感を醸成する話の流れとなっているか (論理に飛躍がなく、かつ根拠に漏れがないか、聞き手の前提知識・理解度を踏まえ、話の流れが構成されているか)
ボディの表現はシンプルで、一目で理解できるか
上記二つの要素が欠けている場合、「3. 企画書の書き方を学ぶ前に:企画書を書く際の問題・課題」でお伝えした問題が必ず起こることになります。
5. 企画書を書く際の実際の頭の使い方や考え方
目次や内容も分かったということで、さぁ書き始めようと思っても、どのように考えていったらよいかわからないというのが実情かと思います。
企画の内容を完成させるためには、企画書の目的を確認しつつ、論点を洗い出したうえで仮説を構築し、検証を重ねていく必要があります。この一つ一つのステップが特に時間を要する箇所かと思いますが、これらを実務レベルで適切にこなせる方は少ないかと思っています。 (外資コンサルであっても、数々のプロジェクトにおいてマネージャーやさらに上位のパートナー等にみっちりしごかれて、何年もかけて当スキルを完全習得していくのです)
上記のような問題に悩まされている方には、下記「企画書・提案書の考え方」のコンテンツをおすすめします。当コンテンツは外資コンサル出身者が作成しており、外資コンサルが研修や実務を通じて体得する内容を学ぶことができます。
具体的には、当資料を通じて、「夢やアイデアを超高速で具現化し、経営陣や顧客からの意思決定を円滑に取り付けるための思考・資料作成技術」を学ぶことができます。資料作成力・ロジカルシンキング力を強化していきたい方、資料作成スピードを爆速化させたい方におすすめの内容となっておりますので、是非ご検討ください。
6. 企画書を書く際のテンプレート
企画書を書く際のテンプレートですが、現在当社で作成中ですのでご期待ください。
企画書のテンプレートではなく、事業計画書や報告書関連の記事となるのですが、企画書を作成していく際の中身やデザインとして参考になる記事を下記にご紹介します。企画書はいかにわかりやすく伝えられるかも重要な要素となりますので、下記記事でご紹介しているスライドを参考に企画書を作成されてみてください。
7. 企画書を書くスピードを上げるには
企画書の作成スピードを極限まで上げるためには、どうすればよいのでしょうか。結論としては以下の3つを行なうことで企画書の作成スピードを向上させることが可能です。
企画書・提案書の考え方を踏まえて思考し、 ⇒無駄に悩んでいる時間を最小化する
企画書・提案書テンプレートを用いて、 ⇒ボツスライド・無駄な資料・しょうもない指摘につながるような汚い資料を増やさない
PPTのショートカットを駆使し、資料作成を進める ⇒「ただ作っている時間」を最小化し、良い企画書の作成に必須な「考える時間」を最大化する
8. 企画書の書き方を学びたいときのおすすめ本
資料作成の基本的な考え方やロジカルに物事を考えるためのスキルを習得するためのおすすめ書籍は下記にご紹介しています。
①企画書を書く際に、外資コンサル級の資料の美しさを実現するためにおすすめ本4冊
さらに知りたい方は以下リンクにて11冊紹介しているので是非ご確認くささい。
プロのコンサルタントが伝授する、わかりやすいスライド作成の極意。グラフ・チャートの描き方、シンプル化のコツなど、グローバルで通用するスライドテクニックを豊富な図解と事例で解説。問題と解答例つきの練習問題も収録した、プレゼン力向上の一冊 | ||
ベストセラー『外資系コンサルのスライド作成術』の実践編。コンサル現場で実際に使われた100点のスライド実例と、優良事例46点の解説を収録。数値表現、論理展開、プロジェクト全体像の伝え方など、コミュニケーション力向上に役立つ技を公開する実践書。 | ||
外資系コンサルティング会社で培った、説得力のある論理的資料作成の原則とテクニックを公開。低クオリティ資料の作り方から卒業し、生産性を大幅にアップさせる手法を解説。資料テンプレートも収録した、ビジネス資料力向上の実践書。 | ||
マッキンゼー流の高いプレゼンテーション力を解説。課題解決プロフェッショナルに求められる、資料作成から実演までの「考え方」と「伝え方」の全てを公開。経営戦略から販促まで、目的に合わせた提案内容の着想法と、説得力のある伝え方のコツを詳述。 |
②企画書を書く際に、問題解決や論点/仮説思考等を身に着けたいときにおすすめ本8冊
外資コンサルは基本的に以下の書籍で紹介されている思考方法を実践を通じて身に着けています。以下で紹介している8冊は経営コンサルの英知が詰まっており、企画書スキルを上げるうえでは必読と言えるでしょう。
仕事を変革する決定版!問題解決の全プロセスを体系化し、現場で即実行可能な技術・作法を解説。トヨタからソニーまで導入、2万人が学んだ内容を一冊に。ビジネススキルを根本から鍛え直し、真の問題を見極め、効果的な解決策を導く力を身につける。 | ||
マッキンゼーとビジネス・ブレークスルーが結集し、経験・時間に縛られず「仮説→検証」で最速の解を導く術を解禁。大前研一の推薦も受け、事業の全景を捉え、強力な仮説を立てる技術を提供。現場で即戦力となる7つのステップと独自の戦略で、どんなビジネス問題も解決へ導く。 | ||
イシューから着手すれば、やるべきことは100分の1に。脳科学×戦略コンサル×ヤフーの三つのキャリアを持つ著者が、問題解決の一連のプロセスを「イシューの見極め」から「仮説立案」「分析」「伝達」までを徹底解説。AI×データ時代に価値ある変化を生み出すプロフェッショナルのための必携書 | ||
ハード思考での問題解決法を詳細に解説する上巻。元マッキンゼー著者による25年の経験と実戦から磨き上げた技術を、事例やチャートを豊富に使用し解説。プロフェッショナルの知的生産性向上を目指し、読みやすいオールカラー誌面で実践的なアプローチを紹介します | ||
ソフトスキルに焦点を当て、問題解決の深層に迫る下巻。仕事の思考様式からマインドマネジメントに至るまで、元マッキンゼー社パートナーが豊富な事例とチャートを用いてオールカラーでわかりやすく解説。日々の業務から経営改革に至るまで、あらゆるシーンで活用できる内容 | ||
『仮説思考』著者が解説する、効果的な問題解決の極意。25年のBCG経験から論点思考を公開。真の課題を見極め、無駄を省き、成果を最大化。一流コンサルタントの技術を、日常の業務や管理に応用。この一冊で、価値ある問題解決へと導かれる | ||
仮説思考で作業量激減!BCG元日本代表内田和成が明かす、3倍速で成果を出す秘訣。情報過多は逆効果とし、答えを急ぐ現代に仮の結論から始める仕事術を提案。20年の経験から生まれた問題解決法で、効率的な意思決定を。 | ||
「ふわっとしている」「既視感がある」「ピンとこない」 誰かにそう言われたら。言いたくなったら。 解像度が高い人は、どう情報を集め、なにを思考し、いかに行動しているのか。 スタートアップの現場発。2021年SpeakerDeckで最も見られたスライド、待望の書籍化! |
③企画書を書く際に、事業の現状分析でおすすめ本6冊
企画を行なうには正しく現状を分析できていることが前提となります。しかし、現状分析は正しい行ない方を習得できていなければ、やたらと時間だけがかかり、対してほしい情報が得られないという結果がしばし起こります。そのような事態を避けるときに参考となるのが下記書籍となります。
ビジネスDDの進め方や留意点をステップごとに解説。第4版では業種別DDのポイントやベンチャー企業に対するDD等を含む派生型DDの章を追加。こちらの本の分析の技術を踏襲すれば、外資系コンサルレベルの事業分析が可能となる一冊。 | ||
プロの調査技術、Web検索からソーシャルリスニングまで多様な手法とケーススタディを紹介。基本流れ、情報収集・作成の9つの技法を用い、断片的な事実から意思決定に役立つ洞察を抽出する方法を公開 | ||
この本があれば、あなたの分析力は次のレベルへ。実践的な枠組みと事例から学ぶ、複雑な問題を解き明かす戦略的思考の極意 | ||
企業再生のプロが教える実践テクニック37を紹介。経営分析の新しい視点を提供するこの本で、「数字のウラ側を読み解く技術」を身につける。冨山和彦氏とIGPIの豊富なエピソードに基づく解説は、まるで物語を読むように理解でき、すべてのビジネスパーソンに必要なスキルを提供。現実の修羅場で培われた知識で、あなたの会社や取引先の真価を見極める力を養います。 | ||
「評価される企業」に必要な条件は何か。定性的データと財務データを結びつけ、勝ち残るための意思決定への実践指針を提供。新会計基準に対応し、ケーススタディも全面刷新。 | ||
事業デューデリジェンスを広く解説した実践ガイド。M&Aの買収側、中小企業経営診断、事業性評価の基本から専門技術まで体系的に整理。専門家だけでなく、初心者にも分かりやすい言葉で説明。外部環境分析から技術・情報システムの分析まで、現状分析の具体的手法を網羅。経営課題の抽出から結果活用までをカバーする必見の1冊 |
④企画書を書く際に、マーケティング観点でサービスや商品の現状分析でおすすめ本6冊
事業単位からさらにサービスや商品単位で分析する際に役立つの本が以下です。いまでは一般的なりましたが、やはりB2BでもB2CでもC2Cでも当該サービスや商品を利用する/購入する顧客がどのような人なのか、それらの人々がどのような行動や思考で購入や利用に至るのかを可視化しましょう。
顧客体験向上には部門間連携が不可欠。本書は顧客体験の課題を可視化し、連携を促進するためのマッピング手法を解説。ダイアグラムの原則から作成プロセス、主要なマップの種類までを詳述。製品・サービス関係者に役立つ実践的な一冊 | ||
「顧客視点で考える」ことを体験するワークショップ形式の書籍。8ステップでカスタマージャーニーマップを作り、ペルソナを立ててマップの精度を高める方法を解説。先進事例と作成ツールも収録。顧客体験の改善に役立つ実践ガイドブック | ||
Webアンケート調査の設計から分析までの実践的なノウハウを解説。アンケート作成時の失敗例や陥りがちな罠、効果的な集計・分析手法などを豊富な事例とともに学べる。データ活用を実務で行うマーケターや企画者に役立つ一冊 | ||
一人ひとりの「N=1」の深い理解から、未購買層の顧客化、ロイヤルへの育成を実現する「顧客起点マーケティング」の理論と実践。ターゲットを可視化する独自フレームワーク「顧客ピラミッド」「9セグマップ」の活用法を公開した画期的な一冊 | ||
10万人の消費者リサーチを重ねた著者が、消費者の本音を"聞き出す"インタビュー技術を完全公開。言語だけでなく非言語情報の読み取り方、対象の選び方、安心して話してもらうコツ、語りにくいイメージを探る技法などを詳述。マーケッターに最高の実践ガイドブック | ||
顧客を見失った経営の危機から脱却する方法を提唱。顧客の心理・多様性・変化を捉える独自の3つのフレームワークを紹介。大手企業からスタートアップまでの実例を交えながら、顧客起点で事業を成長させる経営論を解説する。 |
⑤企画書を書く際に、業務・コスト構造・財務の現状分析や改善で役立つおすすめ4冊
事業を行なう、サービスを提供する際には、適切なオペレーションができているかが重要です。また、それらが数値に落ちた時にどのようなコスト構造になっているか、利益は出ているかを理解する上では以下のような書籍を参照するとよいでしょう。
企業の業務改革において不可欠な「ビジネスモデル・オペレーション・キャパシティ」の視点から、実践的な改革モデルを解説。本社機能から営業、生産、R&D等の個別業務改革まで網羅。自己診断チェックシートも収録した、経営環境変化に対応する必携の一冊 | ||
業務改革プロジェクトの成功率9割を誇る著者が、日本企業で直面する実務上の課題への対処法を実例を交えて詳述。トップ層の巻き込み方、調査のポイント、抵抗勢力への対峙など現場の生の声を盛り込んだ実践書。「普通の人」のための業務改革の教科書 | ||
戦略コンサルティング企業が初公開する間接材コストの徹底削減手法。世界の企業で実証済みの具体的アプローチを項目別に解説。印刷、物流、IT、広告など主要コストの適正化の進め方を詳述。短期で収益改善を実現する経営の専門書 | ||
会計と経営戦略を結びつける実務書。会計の戦略実務への展開と問題解決への応用を、CFOの役割を含めて詳述。実務家や学生に即戦力の知識を提供し、実務ノートでは経営の現場を生々しく描写。会計を戦略に活用したいすべての人へ。 | ||
M&Aプロセスに不可欠の財務DD業務の全貌を明らかにする好評書の改訂。カーブアウト時のDD,買収価格を見据えた財務モデルの利用や価格調整などとの関係まで詳解 |
⑥企画書を書く際に、DXにあたっての現状分析やDX手法で役立つおすすめ3冊
いざDX!と言われたとしても、そもそもDXって具体的に何をすればよい?という状況に陥るかと思います。その際に役立つのが以下の書籍となります。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本から生成AIの業務活用まで徹底解説。アナログからビジネスモデル変革までの道筋と、豊富な成功事例を図解で分かりやすく解説。専門知識不要で、自社のDX推進の手がかりが得られる実践的な入門書 | ||
中堅・中小企業のDX導入を徹底サポート。独自ツール「DXジャーニーマップ」を使った目標設定から実行プロセス、おすすめデジタルツールまでを解説。中小企業特有の課題と解決策、業種別のマップ例も収録。自社のDXイメージをつかみやすい実践書 | ||
顧客を見失った経営の危機から脱却する方法を提唱。顧客の心理・多様性・変化を捉える独自の3つのフレームワークを紹介。大手企業からスタートアップまでの実例を交えながら、顧客起点で事業を成長させる経営論を解説する。 |
⑦企画書を書く際に、戦略策定で役立つおすすめ7冊
事業単位で企画書を書く際には、戦略論の理解は欠かせません。以下の書籍を読むことで、事業戦略・事業開発の神髄を理解することができます。
「ファイナンス×戦略」で“稼ぎ続ける組織”をつくる。 マッキンゼーで長年活躍してきた著者による、企業変革の新発想──。 [味の素、富士フイルム、日立製作所、オムロン、資生堂、アサヒ、コニカミノルタ…] 有名企業のケーススタディも多数掲載! | ||
成功する事業開発の全手順をこの1冊で。アイデアから計画書まで、一気通貫の3×3ステップで解説。新規事業創出から既存事業革新まで、あらゆる場面で活用できるスキルを提供。失敗回避のコツから行動指針、得られる成果まで、各章で実践的な知見を紹介。ビジネス一般にも応用可能な知見・スキルが身につく、事業開発のバイブルです | ||
ローランド・ベルガーの実践派コンサルタントが明かす、戦略作りの秘訣。『現状分析』から『アクションへの落とし込み』まで、現場で真に機能する戦略立案の全プロセスを初歩から解説。カゴメやBMWなどの事例を通じ、実践的なノウハウを惜しみなく公開。本書のゴールは知識の獲得ではなく、実際に職場で活かせるスキルの習得。章末のワークを通じて、読者は「使えるノウハウ」を身に付けることができます | ||
最新戦略論を網羅し、実務を重視した経営・事業戦略の新教科書。ビジネスモデル論からイノベーション、ストーリー論まで幅広く解説。大和ハウス、P&Gなどの実例を交え、理論と実務の橋渡しをする | ||
企業価値を最大4倍に成長させる経営の"定石"を公開。多くのプロジェクトで実践され、優れた成果を残してきた経営手法を徹底解説。組織の行き詰まりを打破し、ブレークスルーを実現するための具体的なヒントに満ちた画期的な一冊 | ||
オピニオンリーダー大前研一氏が、手本のない時代に最善解を導く戦略的思考法を公開。個人・企業が変革するための「気概」と、戦略の核心である4つのポイントを解説。経営者に求められる先見性の十分条件とは何か。成功のプロセスを自ら考えるための入門書 | ||
世界屈指のマーケターがUSJで実践した「数学マーケティング」を公開。勝利の確率を操作し、どんな困難も乗り越える戦略を導出する技術を解説。市場や消費者理解を深め、高い勝率を可能にする秘密の数式を紹介 |
⑧企画書を書く際に、面白い観点を加える際におすすめの4冊
ロジカルに現状を分析し、論理的な帰結としての結論を導きだしたとしてそれは正しいのかもしれませんが、「これはおもしろい!」と思わず唸る企画には、誰もが予想できない/考えつかない視点や材料が必要となります。そんなときにおすすめの書籍は以下となります。
社会学×デザインシンキング×マーケティングの三位一体アプローチ。生活者の現場取材から人間理解を深め、創造的な発想によりユーザーに新しい価値を提供する商品・サービスを生み出す「生活者起点イノベーション」の体系化した入門書 | ||
元任天堂の企画者が「人が動くしくみ」を大公開!ゲームを題材に、商品・サービスに「ついやってしまう」仕掛けを体系的に解説。企画・マーケティング・開発者に役立つ発想法を、ビジネスシーンに活かすコツも紹介する入門書。人の心をつかむ秘訣がわかる! | ||
『Wiiのプレゼンを最も数多くした男』が明かす、コンセプトのつくり方。新しい価値観の発見から、その価値を伝える方法までを解説。起業、商品開発、サービス提案からNPO活動まで、あらゆる創造活動の出発点。コンセプトが明確であれば、差別化やデザインは自然と決まり、関わる全員がブレずに価値ある成果を生む。新たな価値を世に問うすべての人への指南書 | ||
コンセプトの重要性を深掘りし、誰もが実践できる具体的なメイキング手法を紹介。著者の豊富な経験を基に、発想から具体化までのプロセスを初心者にも理解しやすく解説。企画・提案で悩む全ての人へ、クリエイティブな思考を引き出し、言語化する力を育てる一冊 |
⑨企画書を書く際に、M&A・アライアンスを検討したいときにおすすめの本
M&Aを行なう際には理想的なプロセスがあります。以下の本を読むことで検討を適切に進めることができるようになります。
⑩コンサル自体を理解したい方へおすすめ本
コンサルティングファームの実態や実際にどのように仕事を行なっているかを理解するには以下の本がおすすめです。
9. 企画書を書く際の必須アイテム
企画系人材で以下のアイテムを揃えていないのは、出だしからスタートダッシュを切れていないのと一緒。オリンピックの陸上をスニーカーでは走っているのと一緒です。ストレスフリーで快適に資料成を行なえるように設備投資は必須です。
PPTで資料作成を行なう際のPCでこれに勝るものはない。外資コンサルのPCでThinkpadを採用している企業は多く、自分もこのPC一択。最強。神 | ||
外で作業をする際には必須アイテムのモバイルモニター | ||
外用の充電器はこれが最強。やや重いが、モバイルバッテリーにもなるので充電場所がないという非常時にも安心。 | ||
家で作業する際には、2画面ひらけるワイドモニターが必須 | ||
家で作業する用のでかいモニターにつけて、自由自在に角度や高さを変えられ、最強 | ||
家でiphoneとApple watchとAirpodsを同時に充電するのに使ってます。スタイリッシュでかっこいい。たたむと、真四角の獄門彊みたくなります。 | ||
家でずっと座ったまま作業をしていると、足がつかれてくるので自分はスタンディングデスクで、立って作業をすることもあります。眠気防止と健康にもよいです。 | ||
椅子は天下のエルゴヒューマン。企画書を書く人材ならエルゴヒューマンで決まり。外資コンサルはエルゴヒューマン。 | ||
外で作業をしているときに電話やWEB会議が入る方は多いかと思いますが、そのときには神アイテムとなります。外がうるさくても騒音を拾わず、自分の声だけを拾ってくれるため、相手は快適に電話を行なうことができます。家でも子どもの声やテレビの音をもひろわないため、最強。神。 | ||
上記ヘッドセットに「PC接続用に専用BluetoothドングルのBT700が付属」したもの。 | ||
上記Poly Voyager 5200の充電ケース。当然のことながら持ち運びの観点からも充電ケースは必須 |
12. 企画書を書き方を学んだ後のおすすめ記事
今後のキャリアを検討中の方はぜひ「キカクのミチシルベ」をご確認ください。事業会社⇄コンサル⇄独立を自在に行き来したい人が「戦略的にキャリアを再設計」する実践メディアとなっています。
具体的に、コンサルへの転職をお考えの方には、【完全ガイド】コンサル 転職 エージェントおすすめ8選|2025最新をぜひお読みください。大手企業やスタートアップの経営企画/事業企画ポジションに転職をお考えの場合は「【完全ガイド】経営企画 転職エージェントおすすめ5選|2025最新」がおすすめです。
また、「これから独立し、フリーランスとして活動を予定」している方には「【完全ガイド】フリーコンサルエージェントおすすめ14選|2025最新が必見記事となっています。